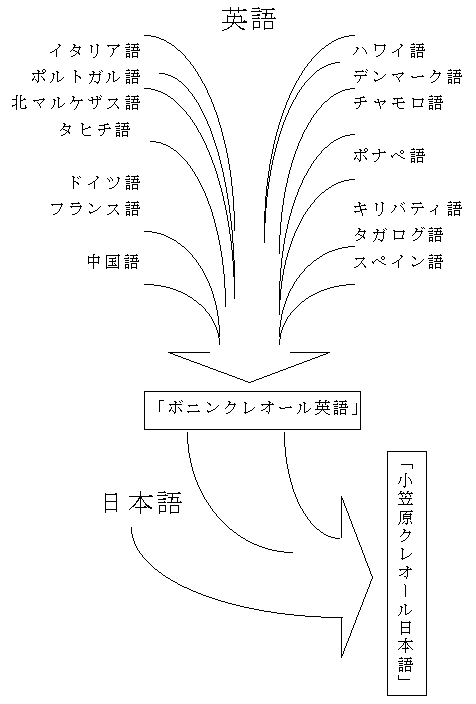
小笠原諸島における言語接触の歴史
ダニエル・ロング(東京都立大学)
dlong@bcomp.metro-u.ac.jp
0. 世界中に見られる言語接触と接触言語
世界の多くの言語は他の言語との接触によって生まれた言語である。むしろ、言語接触を起し、他の言語体系の影響をまったく受けていない言語はおそらく存在しないであろう。人間のさまざまな民族の歴史は他の民族との接触の繰り返しの歴史である。そのために、この地球上で話されている言語のほとんどは、それぞれの長い歴史の中で、何らかの形での言語接触によってその姿を大きく変えていると考えられる。
英語は、千年近く前に、フランス語から大量な単語を取り入れた。このように他言語から導入された単語を借用語(borrowings)と言う。現在の英語では、これらのフランス語起源の借用語を一つも使わずに会話をするのがほとんど不可能なほど、それらは英語の不可欠な一部となっているのである。しかも、英語が経験した言語接触は単語の導入だけにとどまっているわけではない。英語の文法そのものも言語接触によって大きく変えられたのである。また、現代英語そのものはノルマン侵略後に形成されたクレオールに由来すると主張する学派もある(例えば、Bailey & Maroldt 1977参照)。
日本語も同じくらいに言語接触によって変化している。中国語から導入された漢語にしても、西洋の諸言語から入った外来語にして借用語に当たる。しかし、日本語と言語接触の影響は語彙だけにとどまっていない。日本語は文法的にはアルタイ語族(Altaic)と似ているのに、語彙や音韻面においては南方のオーストロネシア語族(Austronesian)との類似性が指摘される。そこで、日本語そのものはこの二つの言語が接触したさいに生じたクレオールに起源をもつ言語だという説が有力になっている(概要はShibatani 1990: 103-118にある)。
一昔前までのヨーロッパの諸言語の歴史をめぐる研究では、現代の言語は昔の言語から枝別れしたという見方が主流であった。たとえば、ローマ帝国の膨張によって、ヨーロッパ各地にラテン語が広がり、そして、ローマ帝国が滅びた後、それぞれの地域に取り残されたラテン語話者が数百年に渡ってラテン語を独自に変えて、それが現在のフランス語やスペイン語やルーマニア語になった。長い間、言語学では、このような「枝別れ説」が主流であった。ところが、現在、これの言語の起源説の定説になりつつあるのは、言語接触による説である。簡単に言えば、ヨーロッパ各地にいた先住民族が支配を受けていたローマ帝国の言語であるラテン語を覚えようとしたが、それぞれの母語の影響が彼らのラテン語に残ってしまい、各地で接触言語が生じたのである。これらの接触言語は当時、標準的なラテン語を話している人には「変なラテン語」、「崩れたラテン語」、「ブロークンなラテン語」として非難されたに違いない。しかし、現在その「変なラテン語」がフランスやスペインやルーマニアの国会や学校で標準語として使われている(Posner 1996:225)。
しかし、世界の多くの言語は元々接触言語であったにも関わらず、接触言語の評判は非常に悪い。18世紀以降にヨーロッパ諸国がアフリカ、南北アメリカ大陸、そしてアジアに植民地を築いたとき、それぞれの地域で、フランス語や英語などの支配国の言語と現地の諸言語との間に接触言語が生じたが、それらは「不完全な言語」とか「破壊言語」として非難された。しかし、実際には、これらの接触言語(ピジン、クレオール言語)は他の言語と同様、文法や音韻の規則があ。
なお、世界中には数多くの接触言語が研究されているが、このほとんどはアフリカやアジアのような非ヨーロッパ人がフランス語や英語などヨーロッパの言語を覚えようとした際に生じたものであった。すなわち、「ハワイピジン英語」や「ハイチクレオールフランス語」などの接触言語が多いが、非ヨーロッパ系の接触言語はさほど多くない。
本論文では、小笠原諸島で起きた言語接触の歴史を振り返り、接触言語が形成された可能性を追究したい。この島々で起きた言語接触は一度にとどまらなかったように、接触言語も一つだけではない。すなわち、小笠原諸島では、2回にわたって接触言語が形成された過程を考察する。
小笠原諸島の言語接触に関する資料はほとんど皆無に等しい。ロングは現在、小笠原でフィールドワークを行っていが、これまでの小笠原に関するさまざまな文献や記録を再検討して、ここで使われていた言語に関する情報を探すことにした。
なお、小笠原諸島のコミュニケーション問題と関わる以下で取り上げる資料の多くは、非常に入手困難なものなので、やや長いものでも、本稿で原文のままで引用する。
1. 初期入植者同士の言語接触(1830-1875)
1. 1. 最初の入植者の言語(1830年)
小笠原諸島の父島に人間が最初に定住したのは1830年のことで、それまでは無人島であった。1830年に住み着いたのは、5人の欧米人と彼らがサンドウィッチ諸島(ハワイ)から連れて行った「カナカ人」(太平洋の諸民族の総称)の女性5人と男性10人であった。
5人の欧米人の母語は、イギリス英語、アメリカ英語、デンマーク語とイタリア語であった。最初に着いたこの太平洋民族が何語を話していたかは不明である。しかし、ポリネシアやミクロネシアの場合は、何千キロと離れた民族でも、その会話の相互理解度はかなり高く、しかも語彙だけなら相互理解度はさらに高まる。
この最初の入植者の来島から、数年のちに、他の言語を話す入植者が集まってきた。
したがって、この島には、入植当初から複数の言語を母語とする人が住んでいたこととなるのである。そして、ある一つの言語の話者が人数的に優勢だったわけではなかった。英語、あるいは英語をベースとする接触言語が島の住民の共通言語となっていたようであるが、入植者のうち、英語を母語とする人はごく少数であった。
1. 2. ポルトガル語話者の入植者(1837年)
1837年に英国の船ラレー号がボニン諸島を訪れた。その船長マイケル・クインが残した報告には、島民についての記録がある。25人の「最初入植者」に加えて、11人の「後の入植者」がいた。その中には、ポルトガル語の話者と思われる者が4人含まれていた。それは、来島して4年のブラジル出身のジョセフ・アントニオ、同じ4年のリスボン出身のジョン・ロバーツ、1年のアゾレス諸島出身のフランシス・シルバ、そして5年半のケープヴェルデ諸島(Cape Verde)出身のジョン・ブラヴォであった(Quin 1837)。最初の3人は他の記録には登場しないので、この島に永住したかどうか、子孫を残したかどうかは不明であるが、彼らは少なくと数年間この島の住民としてこの社会に参加したことが分かっている。この時点では島の全人口は(カナカ人を含めて)36人であったので、このポルトガル語話者は島で起こった言語混合に何らかの影響(仮にそれは短期的な影響であろうと)を与えたと考えざるをえない。
なお、ここで触れている「ジョン・ブラヴォ」とはジョアキム・ゴンザレス(Joachim Gonzales)のことで、このあだ名は彼がの生まれたケープヴェルデのブラヴァ島(Brava)に由来する。彼と彼の子孫はこの島に多大な影響を与えている。この時点でも、島全体の6人の子どものうち、3人は彼の息子であった、と記録されている(Quin 1837)。このゴンザレス家の英語化を示唆することはいくつかある。一世のジョアキムは「ジョン」という英語名を使っているし、この3人の息子に英語名(ジョン、ジョージ、トーマス)を与えている。
これらのポルトガル語話者が島のことばに影響を与えた例の一つとして、次の“borras”という単語があげられる。1872年にチョムリーが島を訪れた際、彼はこの単語を欧米系の島民から聞いた。
“I must give a brief account of the tidal wave, or “borras”as the Bonin settlers term it. . .”(Cholmondeley 1915: 125)
この語源は多分、ポルトガル語で「嵐」を意味するborrascaに由来すると推定される。同形の単語がスペイン語にも存在するが、父島におけるポルトガル語話者はスペイン語話者よりも多いことから、ポルトガル語から来た可能性が高いと思われる。
1. 3. 日本人漂流者の記録(1840年)
19世紀前半、この島における言語使用の状況をほのめかす貴重な資料が残っている。それは、1840年に数ヶ月間小笠原諸島で暮らした日本人の記録である。彼らは陸奥気仙郡小友浦(現在の岩手県陸前高田市)を出た6人の水主で、乗っていた船が遭難して、島に漂着した時にその島民に助けられた。彼らは63日間島に滞在して船を修理して自力で日本本土に戻った。日本では事情聴取が行われ、彼らが島で耳にしていた56の単語や語句が『小友船漂着記』に記録されている。
これまで、この単語は英語やハワイ語であろうと言われていたが、1997年の論文で延島冬生が初めて、それらの原形について分析した。彼の分析によると、56語のうち、英語と思われるものは17語で、ハワイ語は39語である。延島は、「無人島に入植してから10年、英語を中心とする欧米語、ハワイ語を中心とする太平洋諸語が使われていたと思われる」と述べている(1997:77)。
延島の56の語源説の中に議論を呼びそうなものもあるが、全体的にはこの分析は言語学的な音対立の規則に基づいた非常に科学的で、説得力のあるものとなっている。
ところで、この資料から簡単に判断できない一つの重要なことは、これらの単語は同一話者から聞かれたかどうかという問題である。日本人の水夫は、17の英語を欧米人の話者のみから聞き、残りの39のハワイ語を太平洋の島民だけから聞いた可能性は否定できるのであろうか。
当時、島における言語使用状況として次の4つの可能性が考えられる。(1)欧米人は英語しか話せなく、太平洋人も自分たちの言語しか話せなかった。つまり、2つの集団は同じ島で生活していながらも、お互いにコミュニケーションができなかった。すなわち、島は「2言語使用社会」であったが、各々の話者は「単一言語使用者」であった。(2)欧米人は太平洋の言語(あるはそれに近いことば)が話せた。すなわち欧米島民は2言語使用者で、太平洋の島民は単一言語使用者であった。(3)逆に、太平洋人だけは2言語使用者で英語(あるはそれに近いことば)が話せた。(4)島では欧米人も太平洋人も両方が話せる接触言語が使われていた。
(1)の「コミュニケーション不在」社会の可能性はほとんど皆無と思われる。漂流者の証言によれば、島には13軒の家があった(辻友衛1995:上37)。他の多くの記録から、島の男性のほとんどは欧米人だったことが分かる。1830年に来島したカナカ人男性の多くはのちに島を離れたことが分かっている。一方、島の女性のほぼ全員は太平洋の人であることも分かっている。すなわち、ほとんどの家庭は、欧米人の男性と太平洋人の女性から成っていたので、この2つの集団との間にコミュニケーションがなかったことは考えられない。日本人漂流者によると、島の人口はわずか38人(男性25人、女性13人、このうち8人は子ども)だったので、この点から考えても2つの集団がコミュニケーションを行わずに生活していたとは考えられない。
(2)の「バイリンガルな欧米人」という説も、当時の社会状況や西洋人の考え方からすれば非常に可能性が低いと言える。男性の欧米人が自分の妻である太平洋人の言語を覚えるということは想像し難い。これは意欲の問題でもあるが、学習環境の問題も大きかった。
(3)の「バイリンガルな太平洋人」の仮説に関しても、疑問が大きい。島の社会におけるこの2つの集団の力関係を考えれば、太平洋人の習得動機が十分だったと言えるかもしれないが、現実問題として彼女らが一般的な英語を学習をせずに自然に習得したということは考え難い。また、小笠原と似たような状況にあった他の太平洋の島々(つまり欧米人と太平洋人が混在していた社会)では、接触言語が発生したケースが非常に多いので、むしろ(4)の仮説が最も自然性が高いと思われる。
漂流者の単語リストの中にも、ハワイ語とも英語とも思えないもので、ピジンである可能性が高いものが含まれている。例えば、「バツバツ」(博馬)は英語のboat、「コウコウ」(料理する)は英語のcook、「ハヤハヤ」(火)は英語のfireから来ていると延島は述べている。もしこれらの語源説が正しいとすれば、ここに見られる二重化(reduplication)を説明しなければならない。英語の原形にはもちろんこのような二重化はない。また、ハワイ語などポリネシア諸語にも二重化はよく見られるが、これらの語源は英語とされている。日本語にも二重化は見られるものの、それは擬音語以外の単語にはほとんど見られないので、このように日本人の漂流者は外国語を二重化させるはずがない。
むしろ、最も可能性の高いことは、これらの単語は、この島で使われていた接触言語からきているということである。太平洋各地で発生したピジンにはこうした二重化がよく見られるので、これは非常に起こりやすい言語現象と言える。
2. 島民の外部との言語的接触
2. 1. 島民の島訪問者と接触する機会(1830年代)
ボニン諸島の住民は非常に孤立していたというイメージがあるが、入植当初からこの島を訪れた船は一年間に数隻あった。セーボレーによると、1833年1月1日から1835年7月1日までの31ヶ月間にポートロイド(現在の父島の二見湾)を訪れた船は22の捕鯨船を含む24隻であった(Clement 1905:190)。その後も、航海船の来島は、父島に住んでいたセーボレーがマサチューセッツにいた親戚と文通するのが可能だったくらいに頻繁であった(Cholmondeley 1915:43-88)。19世紀に、太平洋を行き来した船上では様々な言語を母語とする水夫の共通言語として、あるいは様々な入港する土地の人との意志疎通を行うため、「太平洋船英語」(Pacific Ship English)と呼ばれるジャーゴン(jargon)が使われていた。これは、太平洋各地に広がった「太平洋ピジン」(Pacific Pidgin English) の原形であると考えられている。
これらの船がポートロイド(現在の父島の二見湾)に入港することをきっかけに、父島の島民は、太平洋全域で通用するこの接触言語を耳にする機会があった。このように「太平洋船英語」と接触する時間は短かったであろうが、それは年に数回あって、そして一回に多数の水夫と島民の接触があったであろう。
2. 2. 島を離れて生活する若者(1850年代)
父島を訪れるよそ者も多かったという事実を考えれば、島民は外部の人間との接触は決して珍しくなったことが分かる。つまり、最初の入植から日本人からやってくるまでの数十年間、島民は決して孤立していたわけではないことが分かる。
これと同時に、島民自身が外へ出て暮らすということも決して珍しいことではなかったようである。1851年の春に父島を訪れた英国船エンタープライズ号(H.M.S. Enterprise)のコリンソン船長(Captain Richard Collinson)が島民のチャピンから直接聞いた話を見よう。島を出てよそのところで生活してから再び島へ戻ってきた人がいたことを示唆している。
これ以外にも、成人が一時的に島を離れて外部の者と接触することがあった。ペリーの率いる艦隊の一隻マカドニア号(USS Macedonian)で父島を訪れたジョン・スプロストン少尉(Midshipman John Sproston)の日記(1854年4月20日)には次のように述べ、欧米人島民のトーマス・ウェッブが一時的にアメリカの捕鯨船ボーディッチ号の副船長として島を離れていたことを明らかにしている。
欧米人の乗った船がたびたびボニン諸島を訪れ、そしてその訪問に関する記録を残している。その中には、太平洋人の島民と英語圏の訪問者との間に何らかのコミュニケーションがあった場面が複数ある。しかし、いずれは太平洋人の島民とのコミュニケーションが取れたものの、その人の英語は上手ではなかったという記述がある。これらの接触場面に見られるコミュニケーション手段は一種の接触言語、すなわちジャーゴンやピジンであったと思われる。
2. 3. 1. 太平洋人入植者の場合(19世紀後半)
上記のコリンソン船長が太平洋人の島民との出会いについて次のように語っている。
1853年に父島を訪れたペリー一行の記録にも、太平洋人島民とのコミュニケーションがあったという記述がある。ここでも、太平洋人島民はある程度の英語、または英語を基盤としたピジンを話す能力を有していたことを裏付ける。少なくとも、以下の記録から、彼らは来島したアメリカ人海軍人と話していたことは事実である。
The Otaheitan professed to know the way, . . . . The guides called the place “Southeast Bay”. They stated that it was frequently visited by whalers for food and water, . . . . The guides said that there was no other way of returning except the ravine by which we came. (Ibid. 403-5)
もう1人のタヒチ人の伝達能力に関してはさほど明確ではないが、彼もアメリカ人に情報を伝えている。しかし、それは直接話していたか、それともジャッジの通訳を通じてコミュニケーションをしていたかは定かではない。もし後者の説明をとるなら、タヒチ(Tahiti = Otaheite)とマルケザス諸島(The Marquesas)の言語は相互理解が妨げられないほど近いので、共通言語を持っていなくてもコミュニケーションができたと考えられる。(ヌクヒヴァで使われる北マルケザス語とタヒチ語との相互理解度は50%としている。語彙の類似度は45%から67%とされている(Grimes 1996)。しかしそれにしても、片方の太平洋人が英語を話す訪問者とコミュニケーションをしていたということには変わりがない。
以上の話を整理して、どの内容の情報が伝達されたか検討してみよう。まず、ジャッジがアメリカ人に伝えたことは次の内容である。(1)自分はマルケザス諸島のヌクヒヴァ(Nukaheva = Nuku Hiva, Nuka-hiva)の出身、(2)自分の名前はジャッジ、(3)島の最南端までの距離は3〜4マイル、(4)彼らを案内することのできる仲間を呼びに、息子を行かせた。
次に、タヒチ人が(1)島の最南端への道を知っている、(2)猪の居所は知っている、(3)ジャッジが同行しなければアメリカ人をそこまで案内しない、(4)彼らは猪の近くに来ている、(5)聞かれた場所への道を知っている。
どちらか、あるいは両方の男が、(1)海は現時点より2分の1マイル先、(2)そこは「南東港」と呼ばれている、(3)その場所には水や食料を求めに捕鯨士がたびたび訪れる、(4)唯一の帰り道は来たときに通った峡谷である。
以上の情報は、目の前にある「ここ」や「今」と関係するような単純で説明しやすい内容ではなく、かなり抽象性の高い内容であることが分かる。つまり、彼らには初対面の英語圏の人に対してかなり抽象的なことを説明するだけの(英語)伝達能力があったと言える。一方、アメリカ人は彼らはあまり英語が話せなかったと記述している。彼らは一体英語が話せたのか、それとも話せなかったか、そしてアメリカ人はなぜこのような矛盾する記述をしたのであろうか。その原因は多分、この2人が一種の接触言語を話していたことにあるのであろう。つまり、意志疎通をするだけの伝達能力を持っていたが、その伝達のチャンネルは英語ベースの接触言語だったため、このアメリカ人には彼らのことばは「ブロークン・イングリッシュ」にしか聞こえなかったので、「彼らはあまり英語ができなかった」という記述を招いたのであろう。
これ以外にも、小笠原諸島に暮らす太平洋人の使用言語や英語のコミュニケーション能力に関する記述がある。それは、19世紀後半に島を訪れたイギリス人のキング宣教師が書いた記事にある。それには、母島に住んでいたロビンソン家のカナカ人の乳母であったハイパの使用していたことばについて次のような記述がある。
[Hypa] had never acquired sufficient knowledge of English to understand any except the simplest sentences, and only those who had been brought up by her or had lived in the same house with her could understand her broken language, half English, half Kanaka. (King 1898: 420)
2. 3. 2. 島で生まれた二世の場合(1850年代)
ウィリアムズ(Samuel Williams)はサラトガ号(USS Saratoga)に乗ったペリーの中国語通訳であった。彼がその航海の出来事を日記に書き残した。ウィリアムズ一行が島に着いた初日(1853年6月14日)の朝9:00ごろに、島の青年がやって来てガイドをかってでるという場面がある。
2. 4. 接触言語の発生
実際に父島を訪れた横浜在住のイギリス人ラッセル・ロバートソンが島民の言語使用能力について次のように書いている。
まず、接触言語が生じる必要性がなければならない。小笠原は孤立していなかったことを上で述べたが、外部との接触に比べて、島民同士の接触の方が当然多かった。この小さな島で島民同士の共通のコミュニケーション手段は不可欠であった。
小笠原住民の言語は英語圏人に通じたので、ピジンであったとしても、それは英語を基盤としたピジンであった。当時、目標言語(英語)を使おうとしていた人々(彼らを習得者と呼ぶ)はいたが、母語の文法などが英語の習得に影響を与えた。(これを言語干渉と言う。)これはすなわち「間違い」として認識されるものである。もし、当時この島にいたのが例えばハワイ人と英語圏人という2つの言語話者集団だけであったとすれば、ハワイ人はやがて自然に自分の間違いに気づき、母語話者並みの英語に近づいていったのであろう。こういう意味では目標言語の母語話者たちは、習得者にとっての模範話者となっているので、彼らと接触していると徐々に目標言語(この場合は英語)の能力が向上する。
ところが、父島のように多数の言語を話す人がいる場合、状況がもっと複雑化する。例えば、ハワイ語話者Aさんとポルトガル語話者Bさんが目標言語である英語を話そうとしていた。彼らは、それぞれの母語の影響を受けて、Aさんはハワイ語っぽい英語、Bさんはポルトガル語っぽい英語になる。この2人にとって、共通のコミュニケーション手段は英語しかないので、英語の母語話者と話すときだけでなく、2人で話すときにも英語が使われる。このように、模範となる英語話者との接触が少なければ少ないほど、それぞれの非母語話者としての特徴(「外人なまり」など)が固定化してしまう可能性が高い。これが安定的ピジン(stable pidgin)の形成へとつながる。そして、このピジン英語を耳にしながら育つ子供(2世)がこれを母語として獲得し、より均一性の高く、複雑な文法をもったクレオール言語が生まれるのである。
私は、19世紀の父島で、ピジン英語が発生し、そしてこれから発達したクレオール英語が島生まれの2世の母語となったという推測を裏付ける証拠は十分あると考える。図1の「ボニンクレオール英語」(Bonins Creole English)は英語が上層言語(superstratum)となった。そして太平洋やヨーロッパの複数の言語が基層言語(substratum)となった。図の下にあるもう一つのクレオール言語はこの論文で後に取り上げる。
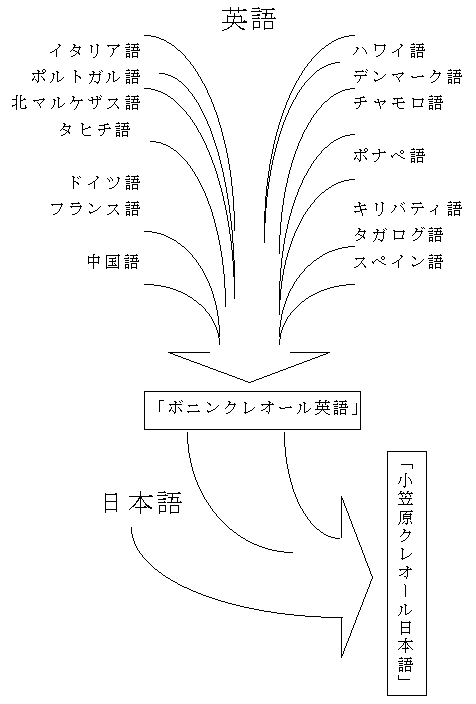
3. 島民の識字能力
識字は言語に対する規範意識(標準語意識)を支える、あるいはそれを強めることにつながる場合が多い。しかし、この島の言語面の歴史において、識字という厄介な要因を考慮しなくても良い。第一世の島民のほとんどは読み書きができなかった。ナサニエル・セーボレーが読み書きもできたことは、彼がマサチューセッツにいる親戚宛てに書いた手紙から分かる(数通はCholmondeley 1915:43-88で複写されている)。彼は来島してから毎日日記をつけていたとされているが、その日記は1872年の津波で流された(Cholmondeley 1915:126)。
また、ロバートソンが1875年11月に父島を訪れたとき、識字能力があったのはイギリス人のトーマス・ウェッブだけだったと述べている。
1876年から日本人による入植が本格化した。当時、父島と母島を合わせた人口は66人と記録されているが、1878年末には、日本人入植者は(母島の一集落を含んで)194人にのぼり、はるかに先住移民の数を上回っている。1900年には、父島の総人口は2366人まで急増している。
4. 1. 島での英語による学校教育(19世紀末)
小笠原が日本の領土になり、日本語が入ってくることによって、英語が衰えたという意見が文献に登場するが、これは必ずしも正しい見方とは言えない。その理由は、(1)日本語が入ってくる以前にも、島で使われたのは英米の英語とは異なる独特な英語(ピジン英語、のちにクレオール英語)だったと思われる、(2)日本の領土となった後でも島では日本語だけではなく、英語による教育も実施された、(3)島で英語による教育が始めて行われたのは日本の領土となった後のことで、それ以前は学校もなければ文字を習う人もいなかった。
小笠原の歴史を中心にして書かれた英語の本はチョムリー著のThe history of the Bonin Islandsの一冊のみである。その中で、以下のように、英語教育は行われなかったと述べているが、これは正確な情報とは言えない。
ジョセフ・ゴンザレス(Gonzales, Joseph)は一八七一(明治四年)四月一五日父島ピール島の大村(イエロービーチ)に生まれ、日本にわたり、神戸の日本聖公会の神学校を卒へてから、当時東京にあった日本聖公会東京南部地方基督牧師のウィリアム・オードのすすめで再び小笠原に渡来する。[中略]彼は早くより小学校児童や村の青年に英語を教えたりしているが、その篤実な性質のため村民から多大の尊敬を受け、選ばれて大村村民総代として村の自治のために働き、島の社会教化事業に大いに貢献している。(大熊良一1966:240)
4. 2. 日本本土での教育を受けた欧米系島民(1885-1920年)
上で見たように、島の若者が複数ハワイで教育を受けたが、ボニン諸島が日本の領土になった後でも、島を離れて教育を受ける島民が複数いた。一つの例がジョン・セウォール(John S. Sewall)の本にある。セウォールは1853年にペリー一行と一緒に島を訪れた。
彼が1905年の本の中で、この半世紀の間に、ボニン諸島を訪れた人には一回しか出会ったことがないと語っている。それは、島が日本領土になった後、横浜の学校でナサニエル・セーボレーの孫娘を教えたアメリカ人の女性教師である。彼女が来島した時期は明らかではないが、島に500人の日本人がいたという情報が正確ならば、これは日本人入植者が入った直前の1885〜86年ごろだったと推測される。1885年の父島の人口は461人で、翌年は598人に増え、世紀末には小笠原諸島全体の人口は5500人に膨らんでいた。
一方、日本本土へ渡り、日本語による教育を受けた人もいた。上でも述べたように、ジョセフ・ゴンザレスは日本公聖会の神戸伝導学校を卒業してから島に戻り、教育と宗教活動に専念した。
4. 3. バイリンガリズムとダイグロシア
大正時代初期には、欧米系の子供はバイリンガルになっていた。そして、次の日本人開拓者二世の回想録によると、島の欧米系社会はダイグロシア的になっていた。ダイグロシアとは公の場で日本語、私的な場で英語を使うという場面による二言語使い分けの状態のことである。
戦争中にもジェリー・セーボレーが日本軍に入り、英語のラジオ放送の日本語を命じられたとNHKのドキュメンタリーで語っている(NHK 1990)。また、Head&Daws(1968)の中でも、戦争直後に欧米系島民がアメリカ軍のために通訳をしていたと述べられている。
5. 米軍による委任統治の時代(1946-1968)
第二次世界大戦中のアメリカで父島の歴史に関する本がアメリカで出版された。その中で、欧米系島民の言語や忠誠心も完全に日本人のものになっていると著者が述べている。
Nothing but Japanese was taught in the schools and the English language was lost. (Gast 1944: 24)
1876年から父島扇浦の公立小学校で英語が教えられていた。そして1902年には小笠原のすべての小学校で英語科が併設された(辻友衛1995:上207)。そして、上でも述べたように、ゴンザレス家の人々がこの時代から公立学校で英語を教え始めて、少なくとも明治末期までこれが続いていた。また、清水理恵子によると、「この教会で英語学校は、ジョセフ・ゴンザレスの息子、ジョサイア・ゴンザレスに引き継がれ、太平洋戦争が勃発する直前まで統けられていた」(1994:6)ということである。
5. 1. 米軍時代以前に成人した島民の話す英語
戦争の直後から、父島が米海軍の統治下に入った。当時本土で避難していた島民数千人のうち欧米系と自称する百数十人だけに島へ帰る許可が降りた。その後、23年間、島が米海軍の秘密基地となり、アメリカ国籍にしろ、日本国籍にしろ、派遣された数十人の兵隊とその家族以外の外部の人の上陸が許されなかった。
そして、日本への返還を控えていた父島に最初に入った記者は1968年に父島を訪れた『ナショナル・ジェオグラフィック』誌のサムプソン(Paul Sampson)と付き添いのカメラマンのモンロー(Joe Munroe)の2人であった。
サムプソンの記事には、島民の言語使用に関する気になる記述がいくつかある。例えば、使用言語の選択についてセーボレー家の男性は次にように語ったと記述している。
また、島民の言語的特徴についても気になる記述がいくつかある。彼は、次のように島民がマサチューセッツなまりの英語で話していたと述べている。
ところで、ロングが1997年12月23日にこの記者に電話で話すことができた。その会話の中で、記者が島民の英語について次のように語っている。なお、ここで強調したいことは、以下のコメントは私が質問する前に自ら述べたことである。
5. 2. 若年層の書いた英語
次に若い人の言語使用能力はどうなっていたかをみてみよう。返還当時の若年層島民の話し言葉の録音はほとんど残っていない。あるいは、それが残っているとしてもその使用許可を得るのが困難である。したがって、ここでは彼らの自筆の作文に見られる言語的特徴を分析してみよう。以下の文は返還直後に欧米系島民の小学校生が書いたものである。
書き手B:“my sisters name is X / my Brothers name is Y / my Father's name is Z”
書き手C:“my sister name is X and my Brother name is Y.”
書き手D:“I felt lonely when my Navy friend were gone. One of my classmade are gone to state.”
書き手E:“I felt lonely. When navy was gonE. / I felt lonely When my navy friend were gone.”
書き手F:“I was play with toy one day [on my] houes with X.”
書き手G:“I feel like I am alone Today So I am going fishing Today and If I caught 7 Fish I will bring It to Teacher. you could fry the fish and eat It.”
次に、この小学生の英作文と1人の中学2年生の作文を比べてみよう。これらの作文はほぼ同じ時期(返還直後)に書かれたのだが、二つの作文に見られる英語は非常に違う。
The ride on the monorail to Haneda Airport was exciting and The airport was very big and beautiful. I was very glad that I was able to go abord the huge ship at I. H. I. The N. H. K. Broadcasting Center was one of the most beautiful places I have seen. The Tokyo Metropolitan Children's House was a very happy place. I had a good time playing with the children. The three schools we visited were the places I like the best during the excursion. The students were all nice and kind to us and I am very thankful.
Kodama was very fast and very comfortable. Atami and Hakone were both unforgettable places.
I felt like I was at home when I was at Ueno ZOO because everyone looked happy and the place was noisy.
Mitsukoshi was a very big store but I like shopping at smaller department stores and putting more time on my shopping. The place where we stayed during the excursion was a good place. The Kuroshio rocks too much and I don’t like it. (染谷恒夫・有馬敏行1972: 164-5)
さて、彼らの第一言語(母語)は日本語だったのであろうか。先に見た1968年のアメリカ人記者が書いた記事によると、日本への返還を控えていた若い島民に、ゴンザレスが日本語を教えなければならないと記述している。
5. 3. 若年層の書いた日本語
次は小学生4年生の日本語の作文である。これは島が日本に返還されてから一年たった1969年に書かれたものである。たった一年という短い間に、この学生が日本語で作文が書けるようになった。これはこの欧米系島民の学生が返還以前からかなり日本語(あるいは日本語を基盤にした接触言語)を話せたことを示唆している。もしそうでなければ、たった一年の間にこれほどの日本語の表現能力が身についたとは思えない。
一年たって
この作文の出だしのところにある「わたしは、アメリカのともだちを見たくなりました。けれどみられません。」はおそらく英語の影響であろう。英語では、「人に会う」ことが“see”と表現されるので、ここで使っている「見たくなりました」はそれを直訳した、いわゆる転移(transference)に当たると思われる。
また、「だって」は逆説の「しかし」として使われている。英語では、「だって」も「しかし」も“but”となるので、これも英語による影響と考えられるのであろう。これも転移という現象に当たる。
次に、「一年まいのこと」に見られる「前」が「まい」になることはこの島の日本語によく見られる現象で二人称の「お前」が「オマイ」になっていることと同じである。しかし、これはこの島で起きた言語接触によって発生した特徴ではなく、むしろ本土の日本語からそのまま伝えられた要素である。父島にやって来た入植者のほとんどは八丈島の人だったが、この/ae/が[ai]になるのはその八丈島方言の典型的な特徴である。
最後に、「そしてアメリカはクーラははいっていませんでした」の文の意味はあいまいであるが、文脈と当時の島の状況を考えると、これは、アメリカ海軍統治時代には島にクーラーがなかった、という意味だろうと想像される。この「クーラ」という単語は標準語では「クーラー」になるが、この長母音の短母音化は島の接触言語の影響によるものなのなのかどうかの判断は難しい。本土の日本語でもこのような語尾の母音の長短の「ゆれ」は外来語の表記にも発音にもよく見られる。それは「データ/データー」のような比較的新しい単語だけではなくて、「コーヒー/コーヒ」のようなかなり定着している単語にも表れる(郡史郎1997:18)。また、これは「行こうか/行こか」のような和語にもや「ベントウ/ベント」(弁当)のような漢語にも見られるので、島民の接触言語の影響による特徴とは断言できない。しかし、英語などの外国語を母語とする話者にとって日本語の母音の長短の区別は難しいのも事実である。
以上、この小学生の作文に見られる言語学的特徴は次のまとめられる。
次に、上の小学生の日本語の作文を中学生のものと比較してみよう。文章は日本の学校で学びはじめてから3ケ月の中学2年生である。表記が不正確なところもあるが、注目したいのは、このエッセイに表れる書き手の第一言語の特徴である。
十月九日はたのしみにしていた日でした。東京に修学旅行に行く日でした。せいとたちはごご二時にはとばに集まりました。三時にくろしお丸がしッこうした。まだ島が見えるうちにせいとたちは一人ずつよいました。わたしは一ばんひどいほうでした。東京わんにはいってからはじめて食事を食べた。十月十一日のごご十二時十分に船はたけしばさんばしにとうちゃくした。バスでしくしゃにいって休すみました。そのよろ新宿にすいとうを買いに行きました。にぎやかのところでした。
十月十二日土曜日から見学をはじめました。浜松町からモノレールにのって東京国際空港までいった。モノレールにはじめてのったのでたのしかったです。はねだはさむかった。よこはまのきれいな公園でべんとを食べた。石川島て大きい船を作くっているのを見た。一つの船にのって見学をした。
日曜日には、はじめにNHK放送センターを見学した。きれいなとこでした。アルバムをおみやげにもらいました。国立競技場には雨がふっていたから十分しかいなかった。児童会館で見学してからお昼のべんとうを食べた。それからあそこにこどもたちとあそびました。バスを三十六かい霞ケ関ビルにむけた。あの早やいエレベーターで一ばん上までいったとき耳がつまった。くもっていてあまりけしきがよくなかった。
月曜日は学校を見学した。わたしは都立大山高校をすきでした。もっとながくいてせいとたちとしゃべってみたかった。練馬工業高校は男子だけの学校でした。見学してから豊島十中にいきました。そこを見せてもらってからせいとだいひょうたちといっしょにしょくじしました。せいとたちはとてもしんせつでいいこでした。かえるときにバスのとこまでおくっていってとてもありがたかった。
火曜日は新幹線こだまにのってあたみのえきに五十分くらいでつきました。すぐにバスにのってはこねにいきました。昼食がすんでから足柄丸であしのこをはしった。ここであのきれいでうたがじょうずなガイドさんとわかれた。ケーブルカーでいおが出ている山の上をとおった時にくさいにおいがした。小田急でロマンスカーにのって新宿にきました。いいきもちだった。新宿えきからバスにのってうたいながらしくしゃにかえった。
見学の最後の日がきた。はじめに上野水族館にいってかわった魚を見た。あるいて動物園を見た。あんまりいろいろの動物がいて見てあるくのがやになった。べんとうを食べてから国立はく物館にいってふるいむかしの物を見た。
もうあんまりあるきすぎてたおれると思いました。ちかてつにのって日本橋のみつこしにいっておみやげを買いました。
十月十七日の午前十時にせいとたちと先生たちがのっているくろしお丸がたけしばさんばしをはなれた。雨がふっていたのでなげたテープもはやいうちにきれました。かえりはぜんぜんよわなかった。十八日になぎだったからデッキの上にいって鳥島を見た。船がみなみにいくほどあつくなるのがわかった。
十九日の午前六時ころわたしのあったかいうちについた。うちでみんなとたのしかった修学旅行についておしゃべりしました。(染谷恒夫・有馬敏行1972:161-163)
もちろん、島民の標準日本語能力にも標準英語能力にも個人差があると思われる。しかし、もっと重要なことはこの中学生の就学年数であろう。彼女は8年生(中学2年生)だから、小学生の書き手に比べて4〜5年標準英語を学習している計算になる。こう考えると、小学生の作文の方はより純粋に彼らの母語を反映していると考えられる。つまり、中学生の作文の方が教室で学んだ標準語の影響を表しているのに対して、小学生は彼らの家庭言語(home language)である小笠原特有の接触変種(contact variety)を反映していると思われる。
欧米系島民自身は自分たちの家庭言語は日本語だったと語っている人がいる。しかし、同じ欧米系島民の中には、自分たちの家庭言語は「日本語と英語をミックスしたもの」というふうに表現している人もいる(瀬掘エーブル1997年9月私信)。
さて、2人の若年層島民が書いた日本語の作文に見られる言語学的特徴を分析した。しかし、先ほど見た英語の作文にはある程度の個人差が見られた。日本語にも個人差があるならば、この2人は果たして典型的な人かどうかは問題になってくる。実は、返還当時に収集された欧米系島民の日本語能力に関するデータがあるので、それを見よう。
5. 4. 米軍時代に生まれ育った若年層の話しことば
上で述べたように、返還当時の欧米系島民の話し言葉を記録したデータは非常に少ないが、まったく皆無ではない。以下の文の内容から、その若年層の話者たちが気楽に話していたことが推測されるので、この文には彼らの日常的な言語の姿が表れているように思われる。返還当時の若年層の話しことばは日本語の文に英語の単語が使われていたと説明する報告が多い。次の文にもそれが見られる。なお、以下では、話し手と話し相手が分かっている場合、それを明示している。
「先生、そんな変なダンス、ミーはやらないぞ。」(同上)
「だらしがないって、なんだい?[中略]じゃあ、だらしがあるようにするんだね、先生は。」(同上)
以下は、返還直後に島を訪れた日本人記者が記録した島民の発言となっている。
「うん。Twentyぐらいゆくのだ。」(同上)
英語の代名詞である「ミー」や「ユー」を使いながらも、日本語の複数形的な役割を果たす「ら」が使われたとされている。これは、学校教師の回想録による文であるが、このような二言語的複合語(hybrid)が実際に使われていたとすれば、非常に興味深い生産である。
「ミーらのティーチャー来るのかい。」(同上)
「ユーは何のティーチャーかい。」(同上)
「ミーのパパ、ラストサンディ、カヌーでフィッシング行ったど。」(同上)
以上、返還当時の若年層島民の話しことばに次の特徴が見られた。
6. 欧米島民のコンペテンスと言語使用
6. 1. 言語干渉と言語接触
以上で見たように、欧米系若年層の日常的な言語には日本語と英語の両方の要素が含まれている。この島の言語状況について最初の研究論文を発表した津田葵はこれを言語干渉(interference)と解釈している。論文では、日本語会話の中での英単語使用を分析した上、次のような話題では干渉が起こりやすいと指摘している(津田葵1988:283-284)。
50代女性:家庭の主婦らしく、衣、食、住に関するトピックや公共施設、気候に関する語彙
小笠原欧米系島民の言語学的特徴は言語干渉によるものという主張にはどういう意味が含まれているか考えよう。言語干渉が起こるためには、話者が二つ以上の言語的コンペテンス(linguistic competence)を持っていることが条件となっている。つまり、彼らが言語干渉を起こしているということは、話者の頭の中には「日本語」と「英語」が二つの別個の言語として入っていることを含意する。
確かに、小笠原の欧米系の人のことばには英語と日本語の両方の要素が見られる。しかし、これは単に彼らが言語的コンペテンスとして持っている(標準)英語と(標準)日本語との間の言語干渉ではないであろう。言語干渉といえば、彼らは英語と日本語の両方を母語としての「言語能力」(あるいは母語に近い言語能力)を持っていることを意味する。そして、その二つの言語能力が、彼らの頭の中でぶつかっている結果、このように両方の要素が彼らの発話に表れるということになる。この状態を図2のモデルで示している。
図2 言語干渉モデル
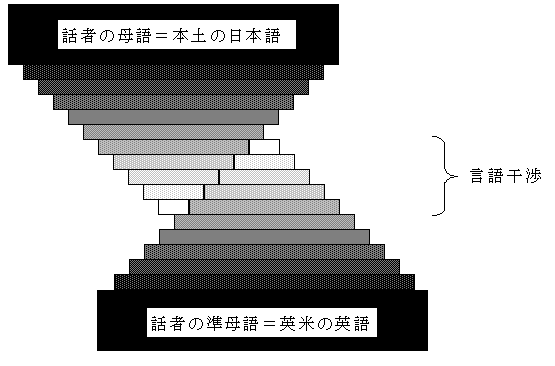
しかし、彼らの言語に見られる現象を説明するには、「言語干渉」よりもむしろ、「接触言語」という概念がいいのではなかろうか。つまり、彼らの頭の中にある言語体系は日本語と英語の二つではなく、むしろ、そのどちらでもない接触言語である。
そして、彼らの日本語、または彼らの英語が自己にも他者にも不完全なものとして認識されるのは、(本土の)日本語も(英米の)英語も彼らの母語とは異なるからである。彼らにとってこれらの言語を使用するということは第2言語(いわゆる「外国語」)を使用することを意味するのである。現在、欧米系島民の中には、(標準)日本語も(標準)英語も使いこなせる人は多く含まれている。彼ら、日本語と英語を使用する「バイリンガル」(2言語使用者)ではなく、日本語、英語、そして第3の言語(「小笠原クレオール日本語」(Ogasawara Creole Japanese)と呼ぶことにしよう)の三つを使いこなすことのできる「トライリンガル」(3言語使用者)と呼ばなければならないのである。
父島で接触言語が発生していた可能性を指摘したのは、「小笠原欧米系島民言語生活研究」という題の卒業論文を書いた清水理恵子であろう。文献調査と現地の聞き取り調査に基づいたこの論文は学部の卒業論文だと思えないほど学問的にレベルの高いものである。
小笠原ではクレオールが2回にわたって起きたのである。1回目の「ボニンクレオール英語」は英語を上層言語とし、その他の複数の言語を基層言語とするものであった。そして、2回目の「小笠原クレオール日本語」は「ボニンクレオール英語」を上層言語とし、日本語を基層言語とする言語であった(図1参照)。
6. 2. 島民の日本語使用能力
さて、以上で見てきた言語を使用していた島民は、自分の言語使用能力についてどう思っていたのであろうか。以下は、1979年に行われた座談会の文字化の抜粋である。参加者は返還当時に学生だった青年層の島民である。
A 家では日本語でしたよ。でも今話している日本語と違う。
B ー番簡単な例をいうと、「お前」と「me」というような日本語を子どものときからしゃべっていた。
司会 みんなは英語も話せるし、日本語も話せていいですね。
A K先生から「お前らは英語も日本語もまともに話せなくて、一番かわいそうだ」と言われた。本当だよね。
C 英語の文法ができていないので、正しく書くことができない。
D そういう意味で、僕たちが一番中途半端だよ。
E 今、現在、僕たちの日本語と英語の理解量というのは半半。Fたちは多少英語の方が多い。僕たちより英語の教育を長く受けているのだから。
F 私たちの年代からみると、Eたちのように、日本語の教育を多く受けた学年の人たちがうらやましいわ。
E Fのもっと上の人たちは完全に英語がわかっている。
F そのかわり日本語が弱い。
B 僕たちは新間を読める程度の日本の教育を受けてきた。しかし、日常生活の中で書類、たとえば税金の申告書等をてきぱきと処理できるか、会社に入って書類整理等を迅速に処理できるか、ということは疑問だ。僕たちの世代では理解できないかもしれないけれど、僕たちの子どもは日本語の社会の中で育つのだから、このような中途半端な問題はない。僕たちはあらゆる面で余裕がなかった。沖縄とは違っていた。
二百十数人からなるこの孤立した島の狭い社会では、島民が共通なコミュニケーション手段を持たなかったことは非常に不自然で、想像しにくい。むしろ、考えられるのは、島民全員が共通の言語体系を共有し、それを普段の場面で使用していたが、改まった場面になると、標準日本語に切り替える人と標準英語に切り替える人との両方の島民(そしてもちろん、両方の方向で切り替えができる人)に別れたという状況である。
返還当時に、島民の日本語使用能力に関するデータが公式に収集された。以下は、調査結果に基づいて作成されたデータ(表1)、およびその報告の一部である。
表1 日本語能力に関する1968年の調査結果
|
|
|
|
高等 |
|
|
|
| 会話 |
|
89 | 21 | 13 | 123 | 67 |
|
|
8 | 33 | 14 | 55 | 30 | |
|
|
3 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
|
|
100 | 56 | 27 | 183 | 100 | |
| 読み |
|
63 | 0 | 1 | 64 | 35 |
|
|
12 | 11 | 7 | 30 | 16 | |
|
|
25 | 45 | 19 | 89 | 49 | |
|
|
100 | 56 | 27 | 183 | 100 | |
| 書き |
|
62 | 0 | 1 | 63 | 35 |
|
|
15 | 9 | 6 | 30 | 16 | |
|
計 |
23
100 |
47
56 |
20
27 |
90
183 |
49
100 |
注:幼児、婚姻女性、米国人等三十五名が除かれている。
〈年当時の日本語能力〉
児童・生徒の日本語は、会話は一応できるが語彙は少なく、又、使い方が不正確であった。読み書きについては、7年生以下の児童は全くできない。8年から日本語の教育が始まるので、9年を終了する時期には、平仮名、片仮名の読み書きは一応できるが、漢字についてはほとんどできない。
〈成人の日本語能力〉
戦前、日本の学校で教育を受けた中、高年齢層については、だいたい、日本語の読み書きはできるが、20才代および30才代の前半の者は読み書きはほとんどできない。(東京都小笠原村立小笠原小学校1979)
表1で使っている「一般」とは、戦前の日本人としての学校教育を受けた人々で、彼らの家庭言語であると思われる「小笠原クレオール日本語」以外に、学校で教わった標準日本語を話すことができた。しかし、米軍統治時代の子供はこの家庭言語に加えて、標準英語を教室で教わっているのである。しかし、標準日本語に遭遇する機会はほとんどなかった。
以下の表2は、1986年に行われた民族誌調査の結果の一部である。ここで、日本語能力には年齢層による差以外に性差もあることが示されている。
表2 Arima (1990: 213)による欧米系島民の言語能力の判定
| Age | <20 | >20 | >30 | >40 | >50 | >60 | >70 | |||||||
| Sex | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Jap
Eng |
+
- |
+
- |
+
± |
+
± |
±
+ |
±
+ |
+
+ |
+
± |
+
± |
+
- |
+
± |
+
- |
+
± |
+
- |
6. 3. それぞれの話者の言語レパートリー
欧米系島民の言語は非常に個人差が大きいが、これは表2に見られるような世代差だけではない。上で述べたように、ジェリー・セーボレーさんは19世紀初頭に横浜のキリスト教系の私立学校で英語による教育を受けたが、15歳年下のいとこである瀬掘エーブルさんは島にある公立学校に通ったため、日本語による教育を受けた。エーブルさんは、自分よりもジェリーさんの方は英語がうまく話せたと語っている(瀬掘エーブル1997年9月私信)。
図3は、個人々の話者がどのような言語を使いこなすことができるかを示す言語レパートリーのモデルとなっている。ここで、話者の第一言語(母語)は小笠原の接触言語である。これは日本語を基層言語、ボニンクレオール英語を上層言語(つまり、語彙供給言語)としたクレオール言語であった。
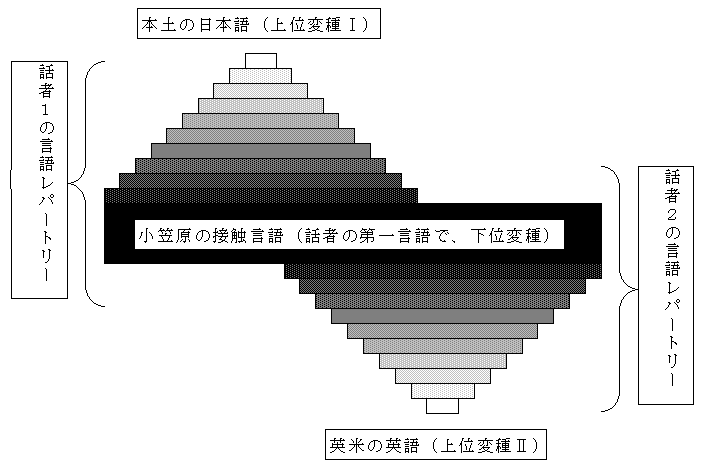
この言語社会の使い分け状況では、小笠原の接触言語が使われたのは、よりくだけた、あるい私的な場面であるので、これは下位変種(basilect)に当たる。一方、改まった場面や公的な場面でよく使われる言語変種は上位変種(acrolect)と呼ばれる。その中間には無数の中位変種(mesolect)がある。このモデルは、複数の言語変種の使い分けを示す、いわゆるクレオール後連続体(post-creole continuum)である。このように、下位変種と上位変種との使い分けが見られる言語社会では、上位変種は普通一つだけある。しかし、小笠原の場合は、上位変種は、(標準)英語と(標準)日本語の二つである。
図3で示していることはただ私が理論的な理屈として考えたモデルではない。こうした言語使用状況があった(ある)ことを示唆する発言が上の6.2.で見た欧米系島民による座談会の記録にも表れている。
以上、父島で2番目に形成された接触言語(小笠原クレオール日本語)について考察した。この接触言語では、日本語は基層言語で、英語は語彙供給言語になっていたが、小笠原諸島が日本に返還さえた20世紀後半にも使われていたことが様々な文献から分かる。
この言語体系がいつ発生したかは正確には言いにくいが、これが米海軍の占領下時代に、島の子どもたちの間で初めて発生したとは考え難い。学校では英語を学んでいたが、もし家の中で一般的な日本語(本土の日本語と同じ非接触型の日本語)が使われていたなら、彼らはこうした接触言語を作らずに、そのままバイリンガルになっただけであろう。むしろ、この時代にはこのクレオール言語がすでに家庭言語として使われていたと考えられる。19世紀後半の明治時代に日本人入植者の数が増え、そして日本人と帰化人との結婚やその他の言語的交流が起こった時代にこの小笠原クレオール日本語が形成されたのではないかと思われる。
なお、上で紹介した資料にもしばしば見られたように、長い間にわたり、欧米系島民の話していることばは「ちゃんとした言語」ではないとされていた。それは日本語として「なっていない」し、英語としても「なっていない」と非難され続けてきた結果、自分たちでもそう信じるようになったのである。言語学的な事実として見れば、彼らの持っている言語は標準語日本語でも標準英語でもない第3の言語体系として認めれるであろうが、これは客観的な学問的なアプローチであり、「正しいことばづかい」が強く求められる世間では通用しない理屈である。
そのため、この数十年間、図3で見た「クレオール後連続体」に沿って、下位変種であるクレオールを使わなくなる傾向が見られる。つまり、かつては家の中でこの接触言語を使い、公な場では標準語日本語あるいは標準語英語を使うというダイグロシア的な多言語使い分けが行われていたが、社会的、または社会心理的な圧力により、この接触言語を使用する場面が減り、片方(あるいは両方)の上位変種を使う場面が増えている。下位変種が使われなくなり、上位変種の使用場面が徐々増えるこうした現象を脱クレオール化(decreolization)という。
7. 結語
以上みてきたよに、小笠原で160数年間に及ぶ複雑な言語接触により、2回にわたり接触言語が生じたと考えられる。19世紀前半に父島で話されていたピジン英語が発達して、ボニンクレオール英語となったと仮定される。そして、日本語との接触によって生まれた小笠原クレオール日本語はピジンではなく、おそらく統語論的収斂という複雑な過程を経て形成されたと考えられる。
本稿では、小笠原諸島に関する数少ない資料を再検討し、わずかであるが、その言語事情についての記述を分析した。現在島民の協力を得て行っているフィールドワークを今後も続け、標準英語と標準日本語に向けての脱クレオール化が急速に進む中で、この2つの接触言語の言語体系を分析して、その実態を明らかにしたい。
謝辞
この論文を書くに当たり、次の方々に協力や助言を得たので、お礼を申し上げます(敬称省略):赤間泰子(元小笠原小学校)、有吉伸人(NHK)、斎藤健治(小笠原小学校校長)、島田正道(小笠原村教育委員会教育長)、瀬掘エーブル、中山善弘(小笠原高校)、延島冬生(小笠原村教育委員会事務局)、長谷川佳男(小笠原高校)、Ross Clark (University of Auckland), Sebastian Dobson, David Goudsward (Dauphin County Library System), Gary E. Jones (University of Southern Mississippi), Peter Muhlhausler (University of Adelaide), Mikael Parkvall (Stockholms Universitet)諸氏。また、最初に小笠原諸島に複雑な言語状況があることを知るきっかけとなった大阪大学の津田葵教授、及び本稿の日本語をチェックしてくれた小西幸男と牛島万にも感謝の意を表したい。
関連文献
有馬敏行(1975) 「小笠原での日本語教育」『言語生活』281:35-41
宇佐美幸二(不詳) 「忘れ得ぬ子等」(出典不詳)
NHK放送局(1990) 『日本とアメリカの間で小笠原セーボレー一族の160年』(NHKセミナー現代ジャーナル、4月30日放送)
大熊良一(1966)『歴史の語る小笠原』南方同胞後援会
郡史郎編(1997) 『大阪府のことば』明治書院
清水理恵子(1994) 『小笠原欧米系島民言語生活研究』共立女子大学日本文学コース卒論
染谷恒夫・有馬敏行(1972)『小笠原村初代村長と校長の記録』福村出版
田村紀雄(1968) 「小笠原の文化とことば」『言語生活』207: 70-74
辻友衛(1995)『小笠原諸島歴史日記』(上、中、下)近代文芸社
津田葵(1988) 「小笠原における言語変化と文化変容」Sophia Linguistica 23-24: 277-285
東京都小笠原村立小笠原小学校・東京都小笠原村立小笠原中学校編(1979)『小笠原小中学校創立十周年記念誌』
東京府(1929)『小笠原島總覧』東京府
西野節男(1988) 「小笠原の返還と島民教育の変化ー「帰国」子女教育の一つの事例として」『国際教育研究』(東京学芸大学海外子女教育センター) 8:1-14
延島冬生(1997) 「小笠原諸島先住民の言葉」『太平洋学会誌』72-73:77-80
橋本(1979) 「日本語教師第一号の哀歓」『びいでびいで』東京都立小笠原高等学校10周年記念誌,54-55
宮本正雄(1979) 「在来生教育の過渡期をふり返って」『びいでびいで』東京都立小笠原高等学校10周年記念誌,62
山本泰子(1968) 「黒潮の島に育つ子ら」(出典不詳)48-53
Arima, Midori (1990) An Ethnographic And Historical Study of Ogasawara/The Bonin Islands, Japan. Stanford University Ph.D. dissertation.
Bailey, C-J. & K. Maroldt (1977) The French Lineage of English. Pidgins - Creoles - Languages in Contact. Ed. J. Meisel. Tubingen: Narr, 21-53.
Cholmondeley, Lionel Berners (1915) The History of the Bonin Islands from the Year 1827 to the Year 1876 and of Nathaniel Savory, One of the Original Settlers, to which is added a short supplement dealing with the islands after their occupation by the Japanese. London: Archibald Constable and Co. Ltd.
Clement, E.W. (1905) Mito Samurai and British Sailors in 1824. Transactions of the Asiatic Society of Japan 33 (contains [Nathaniel Savory] ‘List of Shipping which entered and sailed from Port William, St. George’s, Bonin Islands from 1 Jan. 1833 to 1 July 1835’, in Appendix).
Ehrhart-Kneher, Sabine (1996) Palmerston English. Atlas of Languages of Intercultural Communication in the Pacific, Asia and the Americas. Ed. Stephen A. Wurm, Peter Muhlhausler, Darrell T. Tyron. Berlin: Mouton de Gruyter, 523-531.
Gast, Ross H. (1944) Bonin Islands' Story. With maps, old and new. [Monrovia, California]: Monrovia News-Post.
Grimes, Barbara F., ed. (1996) Ethnologue, 13th edition. Dallas: Summer Institute of Linguistics. http://www.sil.org/ethnologue.
Head, Timothy E., Gavan Daws (1968) The Bonins -- Isles of Contention. American Heritage 19.2:58-64, 69-74.
King, Rev. A. F. (1898) Hypa, the Centenarian Nurse. Mission Field, November: 415-21 (S.P.G.).
Long, Daniel (in preparation) Evidence of Two Contact Languages in the Bonin (Ogasawara) Islands.
Muhlhausler, Peter (forthcoming) Some Pacific Island Utopias and their Languages. Plurilingualisme.
Posner, Rebecca (1996) The Romance Languages. Cambridge: Cambridge University Press.
Quin, Michael (1837) Remarks on Peel Island, Bonin Groupe. (FO17/21 National Library, London).
Robertson, Russell (1876) The Bonin Islands. Transactions of the Asiatic Society of Japan 4:111-143.
Sakanishi, Shio, ed. (1940) A Private Journal of John Glendy Sproston, U.S.N. Tokyo: Sophia University. (reprint 1968, Tokyo: Charles E. Tuttle).
Sampson, Paul (1968) The Bonins and Iwo Jima Go Back to Japan. National Geographic. July: 128-144.
Sewall, John S. (1905) The Logbook of the Captain's Clerk. Adventures in the China Seas. Bangor, ME: Chas. H. Glass.
Shibatani, Masayoshi (1990) The Languages of Japan. Cambridge: Cambridge University Press.
Taylor, Bayard (1856) A Visit to India, China and Japan, in the Year 1853. London: Sampson Low, Son & Co.
Williams, Samuel Wells (1910) A Journal of the Perry Expedition to Japan. Transactions of the Asiatic Society of Japan, Vol. 37, Part 2: 29. 『ペリー日本遠征随行記』(1970) 雄松堂